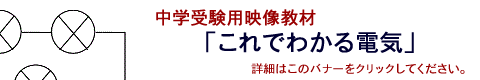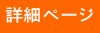■ 自分で勉強する、のは子どもたちにとって実は結構ハードルの高いことなのです。自分で決めた時間に、あまり気がすすまない宿題や塾の復習を広げ、これまたあまりよくわからない問題を解く。ああ、ゲームしたいなあ、と思うでしょ、普通。
■ だから、そういう大変なことをまず自分でやり切る、という習慣が必要なのですが、そういう子に限って、自分の部屋の掃除などしたことがない子が多いようです。洗濯物ができあがったら、お母さんが畳んで、お母さんが引き出しに入れる。
■ 本人はそこから自分の着る物を引っ張り出すだけ。でもまだ、自分で決めるだけいい。これとこれを着なさい、と言わないとだめな子もいる。だめだから、つい手を出す。着せる。準備に手を貸す。
■ そういう子が自分で勉強できるようになるか。といえば、やはりならないものです。だから、勉強は自分でできるようになるまで、親といっしょにやった方が良い。その代わり、もっと身近で自分でやれることは徹底的にさせなければいけません。
■ 自分の洗濯物は自分で畳む。自分の部屋の掃除は自分でする。朝は自分ひとりで起きてくる。
■ そういうことをひとつひとつ自分でできるようになれば、自立が始まるし、そうなれば自分でも勉強できるようになる可能性が高くなります。だから、やっていることが逆なのです。まず、そういう自分の面倒は自分で見る、ところを先にやらせないといけない。
■ そんなことは本当は難しくもなんともないことでしょう? でも、結構できないんです。だから、まして自分で勉強するなど、できない。「勉強しなさい!」と口酸っぱく言ったとしても、実はまだその段階に入っていない子が多いのです。だから、やり方を考えていかないといけないのではないでしょうか。
============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
習い事、今、昔。
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
入学式
==============================================================

==============================================================

==============================================================
![]()
にほんブログ村